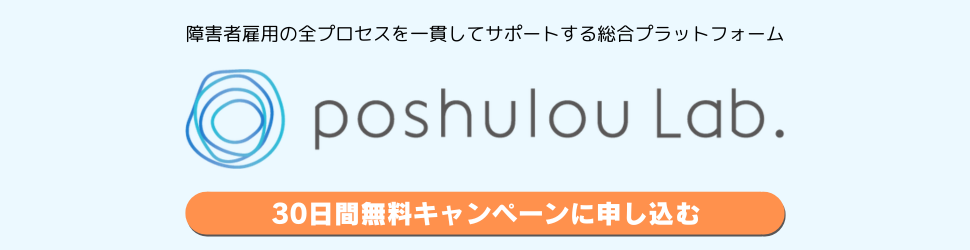Poshulou.Lab お役立ち情報
受け入れ体制の整備〜チーム全体での支援体制構築

法定雇用率の引き上げにあわせて、数値の達成だけでなく「安心して働き続けられる」職場づくりが欠かせません。本稿では、チーム全体で支える受け入れ体制を、準備・受け入れ・継続運用の3ステップで整理します。
はじめに:なぜチーム支援が必要なのか
令和6年6月1日現在、民間企業の法定雇用率は2.5%です 1。2026年7月からは2.7%へ引き上げが予定されています。こうした制度改正に対応するには、雇用率の達成にとどまらず、障害のある方が安心して働き続けられる職場環境の整備がポイントです。
令和5年度障害者雇用実態調査では、多くの企業が「社内に適当な仕事があるか」を最大の課題として挙げています 2。これは、受け入れ体制が個人任せになりがちで、組織的な支援の仕組みが不足している可能性を示します。
受け入れ体制構築の3つのステップ
ステップ1:準備段階での体制整備
採用開始前に「社内の意思統一」「仕事の設計」「外部連携の足場づくり」を同時並行で進めるフェーズです。目的・責任・判断基準を言語化し、必要な役割や運用ルールを先に決めることで、受け入れ後の混乱を防ぎます。
1. 社内理解の促進
- 経営層から現場まで、障害者雇用の意義と法的責任について共通認識を持つ
- 障害のある従業員を5人以上雇用する事業所では「障害者職業生活相談員」の選任が義務付けられています 3
2. 業務の切り出しと整理
- 既存業務を分析し、障害特性に応じた業務を明確化
- 段階的に習得可能な業務フローを設計
3. 支援機関との連携構築
- ハローワーク、地域障害者職業センター、就労移行支援事業所等と早期に連携
- 地域障害者職業センターは事業主支援を無料で提供 4
ステップ2:受け入れ時の役割分担
配属・オンボーディングの初期段階で「誰が・いつ・何を支援するか」を明確化します。本人の特性や希望に基づき、過不足のない支援と評価・フィードバックの流れを設計します。
チーム支援の基本構成
| 役割 | 担当者 | 主な責任 |
|---|---|---|
| 統括責任者 | 人事部門責任者 | 全体方針の決定、経営層との調整 |
| 障害者職業生活相談員 | 認定講習修了者 | 日常的な相談対応、職業生活の支援 |
| 現場指導者 | 配属部署の管理職 | 業務指導、評価、キャリア形成支援 |
| メンター | 先輩社員 | 日常的な声かけ、職場適応のサポート |
| 外部支援者 | ジョブコーチ等 | 専門的な助言、定期的なフォロー 8 |
ステップ3:継続的な支援体制の運用
定例の情報共有・記録・評価で課題を早期に捉え、配慮や業務設計を小さく更新し続ける段階です。社内・外の支援リソースを状況に応じて組み替え、本人の自律度を高めていきます。
1. 定期的な情報共有の仕組み
- 月1回の定例ミーティングを設定
- 支援記録の一元管理と共有
- 課題の早期発見と対応策の検討
2. 段階的な支援の移行

支援体制構築のポイント
合理的配慮の提供プロセス
企業は障害のある方に対し合理的配慮を提供することが義務付けられています 5。これは「特別扱い」ではなく、障害による不利益を除去し、平等な機会を確保するための調整です。
- 本人からの申し出または企業側からの確認
- 必要な配慮内容の話し合い(本人・上長・相談員・人事)
- 過重な負担にならない範囲での実施方法の検討
- 実施と定期的な見直し(評価・更新)
職場環境の整備
職場環境の整備は、配慮の“点対応”ではなく、業務プロセス全体の“面改善”として捉えるのがコツです。物理・情報・人的の3側面を同時に見直し、業務標準(手順書・チェックリスト)へ反映して継続運用できる状態をつくります。改善は“小さく試して、効果を確認して、標準に組み込む”サイクルで回しましょう。
物理的環境
- バリアフリー化(段差解消、手すり設置等)
- 作業環境の調整(照明、騒音対策等)
情報保障
- わかりやすい指示書やマニュアルの作成(図解・写真・動画の併用)
- 視覚的な情報提供ツールの活用(ピクトグラム、進捗ボード等)
人的環境
- 障害理解研修の実施(新任管理者・メンター向けの短時間版を定期開催)
- 相談しやすい雰囲気づくり(相談窓口の明確化・“声かけ”のルール化)
チーム支援体制のチェックリスト
以下は「いま、職場がどの程度“仕組みとして”支援できているか」を点検するための項目です。四半期ごとに関係者(人事・現場管理職・相談員・メンター)で5〜10分のクイックレビューを行い、未達項目は次のアクションへ落とし込みます。目安として、各ブロックで80%以上が「実施済み」なら安定運用、60〜79%は要改善、59%以下は優先課題として対応を計画しましょう。
準備段階
- □ 経営層の理解とコミットメントがある
- □ 障害者職業生活相談員を選任している
- □ 業務の切り出しと整理が完了している
- □ 外部支援機関との連携体制がある
受け入れ時
- □ 役割分担が明確になっている
- □ 本人の特性と配慮事項を関係者が共有している
- □ 段階的な業務習得計画がある
- □ 相談窓口が明確になっている
継続支援
- □ 定期的な面談を実施している
- □ 支援記録を適切に管理している
- □ 課題への早期対応体制がある
- □ キャリア形成の機会を提供している
まとめ:持続可能な支援体制へ
障害者雇用の受け入れ体制は、法令遵守だけが目的ではありません。多様な人材が力を発揮できる環境づくりは、組織全体の成長につながります。特定の担当者に負担が集中しない「チーム全体の支援体制」を構築し、国の方針 10を踏まえつつ主体的に取り組んでいきましょう。外部機関を活用しながら段階的に体制を強化することで、障害のある社員も企業も共に成長できる環境が実現します。