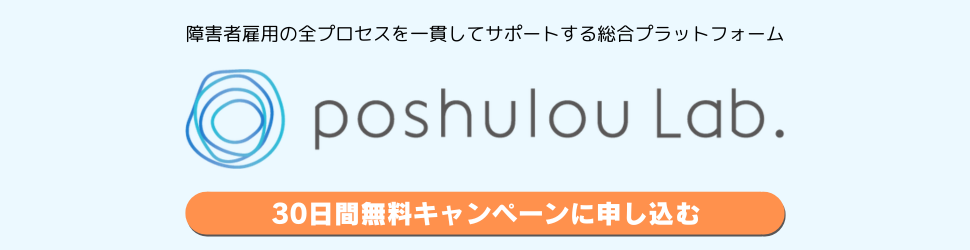Poshulou.Lab お役立ち情報
採用戦略の見直し〜求める人材像の明確化
採用は「義務だから」ではなく、「この人と一緒に働きたい」という意思から。
本コラムでは、求める人材像の明確化と受け入れ環境の整備を軸に、持続可能な採用へと設計を見直す実践策をご紹介します。
本コラムでは、求める人材像の明確化と受け入れ環境の整備を軸に、持続可能な採用へと設計を見直す実践策をご紹介します。

はじめに:採用の成功は「準備」で9割決まる
「とりあえず採用してから考える」という進め方は、本人にも企業にも負担が大きく、定着しづらくなります。 採用前の準備、とくに人材像の明確化と受け入れ環境(業務・人・ルール)の整備が、その後の活躍を左右します。
業務の棚卸しから始める戦略的アプローチ
なぜ業務の棚卸しが必要なのか
「任せられる仕事がない」という悩みは、業務が複雑に混在していることが原因のことが多いです。 業務を細分化して再構築すれば、障害特性に適した職域を創出しやすくなります。
業務棚卸しの実践手法
ステップ1:現状業務の可視化
各部署に以下の観点で洗い出してもらいます:
- 定型的/非定型的
- 単独作業/チーム作業
- 期限の厳格性(高/中/低)
- 必要なスキルレベル
- 作業環境(静/動、対人接触の有無)
ステップ2:業務の再分類(マトリクス)
| 分類 | 特徴 |
|---|---|
| A:定型・単独作業 | ルーティン化可能、マニュアル化しやすい |
| B:創造的・単独作業 | 集中力が必要、成果が明確 |
| C:定型・対人作業 | コミュニケーション頻度が高い |
| D:変動的・チーム作業 | 柔軟性が必要、調整が多い |
ステップ3:職務再設計(ジョブ・リストラクチャリング)※1
各部署に分散する定型業務を集約し、新たな職務として再構築します(例:各部署のデータ入力をまとめて「データ管理スタッフ」を新設)。
業務切り出しの例
事例1:総務部門
- 名刺管理のデータベース化
- 会議室の予約管理と準備
- 備品の在庫管理と発注補助
- 社内便の仕分けと配送
事例2:営業部門
- 顧客データの入力・更新
- 提案資料フォーマットの整備
- 営業資料の印刷・製本
- サンプル品の在庫管理
事例3:製造部門
- 部品の仕分けと補充
- 検品工程の一部
- 作業場の清掃と整理整頓
- 工具類の管理
求める人材像を明確化する5つの視点
視点1:業務遂行能力よりも「環境適応力」
現時点のスキルより、自社の環境に適応できるかを重視します:
- 物理環境(騒音・照明・温度)への適応
- 勤務・休憩リズムへの対応
- 人間関係の密度への適応
- 変化や不測事態への対処方法
視点2:「できること」と「配慮があればできること」の見極め
- 独力でできること:特別な配慮なしに遂行可能
- 配慮があればできること:合理的配慮※2により遂行可能
- 現時点では難しいこと:将来の可能性として検討
視点3:コミュニケーション特性の把握
- 口頭/文書、どちらが得意か
- 1対1は可能/集団は負荷が高い などの傾向
- 即答が必要/時間があれば回答可能
視点4:ストレス耐性と回復力
- ストレスサインの自覚度・対処法
- 回復に要する時間と方法
- 支援者(医療・福祉・家族等)との連携状況
視点5:成長可能性とキャリア志向
- 学習意欲・向上心
- 目標設定の明確さ
- フィードバックの受け止め方
- キャリアビジョンの有無

ジョブマッチングを成功させる実践テクニック
職場実習を最大限活用する方法
職場実習は「選抜の場」ではなく、相互理解と条件づくりの場です。実務に近い環境で (1)観察する指標と(2)学習の機会、そして(3)配慮の検証を同時に回し、 最小限の配慮で最大限の成果が出る働き方を一緒に見つけます。
実習期間の設定目安
- 身体(肢体・内部等)の障害がある方:おおむね1週間
- 知的な障害がある方:おおむね2週間
- 精神・発達等の障害がある方:おおむね2〜4週間
実習中のチェックポイント(毎日の振り返り)
- 業務の理解度・習得速度
- 疲労度と回復の状況
- 職場での人間関係構築
- 必要な配慮の具体化
面接だけでは見えない適性を見極める方法
ワークサンプル法※3の活用
- 作業の正確性・速度
- 指示の理解度(口頭/文書)
- 質問の仕方・頻度
- エラー発生時の対処
アセスメントシートの活用
| 評価項目 | 評価の観点 | 確認方法 |
|---|---|---|
| 基本的労働習慣 | 時間管理、身だしなみ、挨拶 | 実習初日から観察 |
| 業務遂行力 | 正確性、持続力、理解力 | ワークサンプル |
| 対人関係 | 報・連・相の実施 | 実習期間中の行動 |
| 適応力 | 変化対応、ストレス管理 | イレギュラー時の対応 |
支援機関を味方につける連携術
連携の基本原則(共通)
本人中心・最小限共有・役割明確化が基本です。目的に必要な情報のみを共有し、本人の同意を必ず得ます。企業・支援機関・本人の三者で、到達目標・評価方法・連絡窓口を事前に文書でそろえましょう。
- 目的の明確化:「実習評価」「定着支援」「配置転換検討」など目的を先に定義
- 評価の見える化:処理件数・正確率・問い合わせ回数等のKPIを合意
- 定例化:週1回15〜30分のショートMTGで状況確認と次の一手を決める
就労移行支援事業所※4
実習や採用後の定着支援まで一貫して伴走できます。事業所ごとに得意分野が異なるため、業務ニーズとの相性を早期に見極めましょう。
- 初回打合せの要点:得意業務領域/訓練内容と評価方法(定量・定性)/企業内の指導体制
- 事前情報セット:業務内容・成果基準・コミュニケーション手段・休憩/配慮ルール・緊急連絡
- 役割分担の明文化:企業(作業指示/安全管理)・事業所(学習支援/調整)・本人(セルフマネジメント)
- 報告書フォーマット例:業務習得度/必要配慮/成功条件/次回アクション(企業/事業所/本人)
ハローワーク
求人票の段階から業務の具体性と支援受け入れ体制を記載するとミスマッチを防げます。トライアル雇用等の制度活用は実務適性の見極めに有効です。
- 制度活用の流れ(例:トライアル雇用※5):事前相談 → 求人票作成 → 選考 → 計画書作成 → 実施・モニタリング → 評価・次段階へ
- 求人票に書くべき項目:具体的業務・1日の流れ・成果基準/想定配慮/指導担当の有無/選考フロー
- NG例:抽象的表現(「簡単な事務」等)/能力の一般化や断定的な不可記述
地域障害者職業センター
職業評価やジョブコーチ※6支援で、現場での学習と定着を促進します。企業側は教示手順や評価軸を用意すると効果が上がります。
- 職業評価の例:作業の正確性・持続時間・注意配分・対人応対・指示理解(口頭/文書)
- ジョブコーチ導入フロー:申請 → アセスメント → 現場観察 → 支援計画 → 同行支援 → 段階的フェードアウト → 定着フォロー
- 企業側の準備:教示手順書・チェックリスト・観察記録(KPIとひもづけ)
三者連携ミーティングの進め方(テンプレ)
- アジェンダ:前回ToDo/出勤・体調の把握/業務習得進捗/配慮の有効性/課題と対策/次回までの役割分担
- 共有指標(例):処理件数・正確率/必要な声かけ回数/休憩タイミングの適合/本人の負荷自己評価
- 記録のコツ:事実→所見→アクションの順で簡潔に。合意事項は次回までの期限付きで。
ポイント:「支援機関=外部」ではなく、同じ目標に向かうチームメンバーとして関わること。評価と配慮を定期的にアップデートし、本人の強みを活かす配置と学習機会を増やしましょう。
採用プロセスを再設計する
従来型から段階的プロセスへ
従来の「書類→面接→採用」では、実際の職場適応力が見えにくい課題があります。
1. 書類選考(基本情報の確認) ↓ 2. 事前面談(相互理解) ↓ 3. 職場見学(環境確認) ↓ 4. 職場実習(適性評価) ↓ 5. 振り返り面談(課題整理) ↓ 6. 採用決定(配慮内容の合意)
各段階での確認ポイント
第1段階:書類選考
- 就労準備性/希望する配慮/通勤可能性
第2段階:事前面談
- コミュニケーション方法/障害特性の理解度/就労意欲
第3段階:職場見学
- 物理環境への反応/通勤経路/職場の雰囲気への所感
第4段階:職場実習
- 実務能力/職場適応/必要な配慮の具体化
第5段階:振り返り面談
- 本人の意向/職場評価の共有/改善点の整理
第6段階:採用決定
- 労働条件の明示/配慮事項の文書化/支援体制の説明
よくある失敗パターンと回避策
失敗1:「即戦力」を求めすぎる
回避策:3ヶ月・6ヶ月・1年の段階目標、OJT※7計画、スモールステップでの習得
失敗2:配慮の「思い込み」
回避策:本人との対話/実際に試す/配慮内容の定期見直し
失敗3:現場任せの採用
回避策:現場のプロセス参画/配属前研修/メンター制度※8の導入
明日から実践できる7つのアクション
- 業務棚卸しシートの作成(各部署に配布し1週間で回収)
- 職場環境チェックリスト(物理・人的の両面)
- 実習受け入れマニュアル(流れと評価基準を明文化)
- 支援機関連絡リスト(役割と連絡先を整理)
- 配慮事項記録シート(面談・実習での確認事項を記録)
- 現場向け説明会(意義と受け入れ準備を共有)
- 採用スケジュールの見直し(段階的プロセス前提で余裕を確保)
まとめ:採用の成功は「相互理解」から生まれる
企業が一方的に選ぶのではなく、相互理解のプロセスへ。「誰でもよい」から「この人だからこそ」に発想を転換し、適切な業務の切り出し・丁寧なマッチング・段階的プロセスで、採用は組織に新しい価値をもたらす機会になります。
用語注
- ジョブ・リストラクチャリング:既存の職務を分解し、障害特性に応じて再構築する手法
- 合理的配慮:障害のある方が他の方と平等に権利を享受・行使できるよう、必要かつ適当な変更・調整を行うこと
- ワークサンプル法:実務に近い課題で職業能力を評価する方法
- 就労移行支援事業所:一般就労を目指す障害のある方に訓練等を行う事業所
- トライアル雇用制度:試行雇用により適性等を見極め、常用雇用移行を目指す制度
- ジョブコーチ:職場適応を支援する専門援助者
- OJT(On-the-Job Training):職場での実務を通じた教育訓練
- メンター制度:先輩社員が相談役となり成長を支援する制度