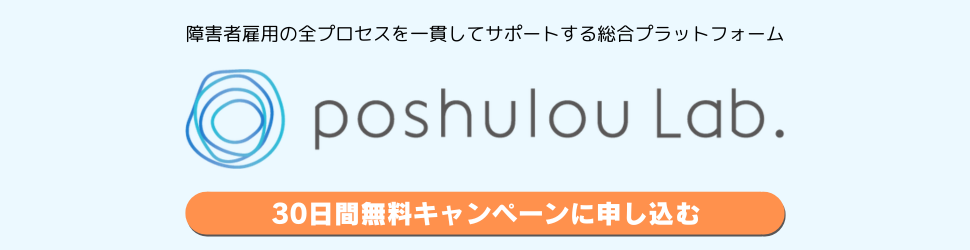Poshulou.Lab お役立ち情報
職場環境が鍵〜精神障害のある方の定着を支える要因

厚生労働省が2024年12月に公表した「令和6年障害者雇用状況の集計結果」によると、精神障害者の雇用数は対前年比15.7%増と大幅な伸びを示しています¹。しかし、採用が進む一方で、精神障害者の職場定着が大きな課題となっていることが各種調査で明らかになっています。
特に注目すべきは、職場環境や人間関係が定着に大きく影響するという事実です。これは技術的な配慮以上に、職場環境そのものが定着の鍵を握っていることを示しています。
精神障害者雇用の現状と課題
急速に拡大する精神障害者雇用
2024年の障害者雇用状況では、全ての障害種別で雇用数が増加していますが、その中でも精神障害者については対前年比15.7%増という結果となりました¹。これは、2018年に精神障害者の雇用義務化が明示されたことと、2024年4月から法定雇用率が2.5%に引き上げられたことが大きく影響しています²。
定着における課題の深刻さ
厚生労働省の令和5年度障害者雇用実態調査によると、精神障害者に対する配慮として「短時間勤務等勤務時間の配慮」が54.3%の企業で実施されており³、体調面での配慮の必要性が高いことが分かります。また、精神障害の特性として、職場環境への敏感さや人間関係での困難さが指摘されており、これらが定着を困難にしている要因となっています。
職場環境改善が定着の鍵である理由
精神障害特有の職場適応課題
精神障害のある方は、症状の変動、疲れやすさ、ストレスへの敏感さなど、他の障害種別とは異なる特性を持っています⁴。これらの特性により、職場の雰囲気や人間関係が直接的に症状や働きやすさに影響を与えるため、職場環境の整備が特に重要となります。
環境要因の影響の大きさ
厚生労働省の資料でも、精神障害のある方への配慮として「職場環境の整備」「コミュニケーション支援」の重要性が強調されています⁴。単なる業務上の配慮だけでなく、職場全体の理解と協力が不可欠です。
職場環境改善の3つのアプローチ
心理的安全性の確保
職場全体での精神障害への理解促進が最優先です。全社員を対象とした障害理解研修の実施により、精神障害の特性に関する正確な情報を共有し⁴、アンコンシャスバイアス(無意識の偏見)を意識化することから始めます。
具体的な取り組み
「職場見学会」の開催や段階的な「職場実習」の実施により、採用前からの丁寧な関係構築を行うことで⁵、入社後のミスマッチを防ぐことができます。これにより、精神障害のある方が安心して能力を発揮できる土台を作ることができます。
相談・支援体制の整備
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の事例では、「会社」、「社員」、「第三者機関(支援機関等)」が連携・協力することが重要とされています⁵。
多層的な支援ネットワーク
定期面談の実施、メンター制度の導入、複数の相談窓口の設置により、いつでも相談できる環境を整えることが大切です。また、地域障害者職業センター、就労移行支援事業所、医療機関(本人同意のもと)との連携により⁵、企業単独では困難な専門的支援を補完することができます。
合理的配慮の適切な実施
厚生労働省の合理的配慮指針では、精神障害者に対する配慮例として通院への配慮、勤務時間の調整、休憩の確保などが示されています⁶。
個別ニーズに応じた配慮
実際に短時間勤務等勤務時間の配慮を54.3%の企業が実施しており³、通院時間の確保、休憩時間の柔軟な設定、ストレス軽減のための環境調整、業務量の段階的調整などが効果的です。重要なのは、画一的な対応ではなく、一人ひとりの状況に応じた個別配慮を通じて、無理なく能力を発揮できる環境を整えることです。

継続的なフォローアップの重要性
入社初期の集中支援
入社初期は特に不安や戸惑いが大きいため、3か月から6か月を目途に定着支援に向けた定期面談を実施し、初期適応を丁寧にサポートすることが重要です⁵。この期間のきめ細かなフォローアップが長期的な定着率向上に直結します。
組織的な支援体制の構築
ジョブコーチ支援により、本人の障害特性や就労状況をより適切に把握し、必要な配慮を実施できたという事例が報告されています⁵。個人の記憶や感覚に頼らず、組織的な支援体制を構築することが重要です。
今すぐ始められる実践ステップ
現状把握と体制整備
まず、自社の受け入れ体制について、相談窓口の有無と機能性、管理職の障害理解度、職場の心理的安全性を点検します。同時に、地域の支援機関との関係構築、社内支援体制の明確化、緊急時対応プロセスの整備を進めます。
段階的な環境改善
短期的改善(1-3ヶ月): 相談窓口の設置、基本的な障害理解研修の実施、既存社員への情報共有から始めます。
中長期的改善(6ヶ月-1年): 包括的な支援制度の構築、組織文化の変革、継続的な改善サイクルの確立を目指します。
取り組みが生み出す価値
適切な職場環境整備により、精神障害者の定着率向上はもちろん、採用コストの削減、業務の安定化、チームの結束力向上につながります。さらに、精神障害者への配慮はすべての従業員にとって働きやすい環境づくりにもつながり、心理的安全性の高い職場は障害の有無に関わらず全員のパフォーマンス向上をもたらします。
また、2024年4月から合理的配慮の提供が義務化されており²、適切な環境整備は法的リスクの回避という観点からも重要です。
おわりに
精神障害のある方の職場定着において、職場環境は決定的な要因です。技術的配慮だけでなく、心理的安全性と包括的な支援体制の構築が不可欠です。これは単なる義務としての取り組みではなく、すべての従業員が能力を発揮できる働きがいのある職場づくりにつながる戦略的投資でもあります。
【参考文献・注釈】
- 厚生労働省「令和6年障害者雇用状況の集計結果」(2024年12月20日)
- 厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」リーフレット
- 厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果」(2024年3月27日)
- 厚生労働省「精神障害のある方と共に働く上でのポイントと障害特性」
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用事例リファレンスサービス」
- 厚生労働省「雇用分野における障害者への差別禁止・合理的配慮」(合理的配慮指針事例集掲載ページ)
【用語解説】
- 法定雇用率: 企業が雇用しなければならない障害者の割合(2024年4月から2.5%)
- 合理的配慮: 障害者が職場で能力を発揮するために必要な環境調整や支援措置
- 定着率: 採用された障害者が継続して働き続ける割合