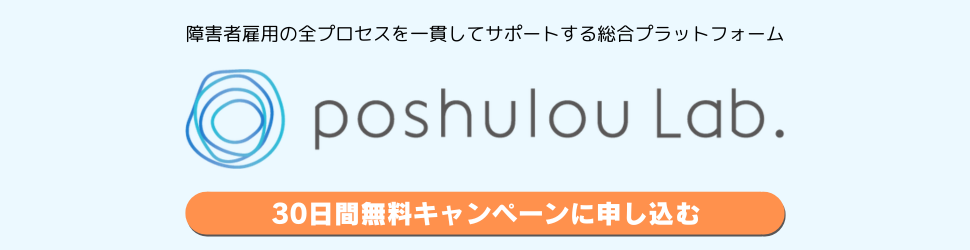Poshulou.Lab お役立ち情報
なぜ今「義務」を超えた障害者雇用が求められる?
単なる法令遵守から価値創造への発想転換

現状を見つめる|あなたの会社の障害者雇用は「つくらなきゃ」ですか?
2024年の法改正により障害者雇用は大きな転換期を迎えています。しかし、多くの企業で聞かれるのは、こんな声です。
「法定雇用率を満たすために、とりあえず採用しなければ」
「合理的配慮が義務化されたから、対応せざるを得ない」
「ペナルティを避けるために、最低限の取り組みをしよう」
このような「つくらなきゃ」の発想で障害者雇用に取り組んでいる限り、本当の成果は生まれません。
根本的な問題|なぜ「義務感」だけでは限界があるのか
「つくらなきゃ」の発想が生む悪循環
厚生労働省の調査によると、現在多くの企業が以下のような課題に直面しています¹
採用段階での課題
- 法定雇用率達成のみを目的とした「数合わせ」的な採用
- 業務内容や職場環境への配慮が不十分
- 本人の適性や意欲より「採用しやすさ」を優先
定着段階での課題
- 継続的な支援体制の未整備
- 職場環境の改善への取り組み不足
- 担当者個人に依存した支援体制
結果として生じる問題
- 高い離職率(精神障害のある方で約50%²)
- 職場全体のモチベーション低下
- 障害者雇用への否定的なイメージの定着
これらの課題は、障害者雇用を「義務として仕方なく行うもの」と捉えている限り、解決することはできません。
発想転換の必要性|「つくりたい」という意思が生み出す価値
では、「義務」から「意思」への転換とは、具体的にどのような変化を意味するのでしょうか?
「つくらなきゃ」の発想
- 法定雇用率の達成が最終目標
- コストとリスクの最小化を重視
- 短期的な問題解決に注力
- 障害のある方への「特別な配慮」という認識
「つくりたい」の発想
- 多様性を活かした組織変革が目標
- 長期的な価値創造を重視
- 持続可能な成長戦略として位置づけ
- 誰もが働きやすい環境づくりという認識
価値創造の実例|公的調査で確認された組織変革の効果
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の研究により、「意思」を持って障害者雇用に取り組む企業では、以下のような価値創造が確認されています³。
1. イノベーションの促進
異なる視点による業務改善
- 業務プロセスの見直しにより効率化を実現
- 新たな視点からの問題発見と解決
- 技術やサービスのアクセシビリティ向上
2. 組織全体のパフォーマンス向上
働きやすい環境の実現
- 業務の標準化と見える化により全体の生産性向上
- コミュニケーション改善による連携強化
- メンタルヘルス意識の向上
3. 企業ブランドの向上
社会的評価の高まり
- CSR(企業の社会的責任)への取り組み評価
- 多様性を重視する優秀な人材の獲得
- 顧客や取引先からの信頼度向上

具体的な価値創造のメカニズム
メカニズム1:「合理的配慮」が「ユニバーサルデザイン」を生む
障害のある方への配慮として導入した取り組みが、結果的に全従業員にメリットをもたらします。
事例:
- 静かな集中エリアの設置 → 全社員の生産性向上
- 業務指示の文書化 → 引き継ぎ効率の改善
- フレキシブルな勤務時間 → 全社員のワークライフバランス向上
メカニズム2:「多様性」が「創造性」を促進
異なる背景や経験を持つメンバーの参加により、これまでにない発想や解決策が生まれます。
効果:
- 従来の「当たり前」に疑問を持つ機会の増加
- 多角的な視点による問題解決
- 新しいアイデアや改善提案の増加
メカニズム3:「包摂的環境」が「心理的安全性」を高める
誰もが安心して働ける環境づくりにより、組織全体のパフォーマンスが向上します。
結果:
- 自由な意見交換の促進
- 失敗を恐れない挑戦的な取り組み
- チーム全体の結束力向上
組織変革のステップ|「義務」から「意思」への転換プロセス
ステップ1:経営層の意識改革
目標:「コスト」から「投資」への認識転換
具体的アクション:
- 障害者雇用による価値創造事例の情報収集
- 経営戦略への組み込み検討
- 全社方針としての位置づけ明確化
ステップ2:組織文化の変革
目標:「多様性」を歓迎する風土の醸成
具体的アクション:
- ダイバーシティ&インクルージョン方針の策定
- 管理職・現場リーダーへの研修実施
- 社内コミュニケーションの改善
ステップ3:システムとプロセスの整備
目標:持続可能な支援体制の構築
具体的アクション:
- 採用プロセスの見直し
- 定着支援システムの整備
- 成果測定とフィードバック体制の確立
ステップ4:継続的改善の仕組み化
目標:組織学習と継続的価値創造
具体的アクション:
- 定期的な効果測定と改善
- 成功事例の社内外への発信
- 新たな価値創造機会の探索
まとめ|変革の時代に求められるリーダーシップ
2024年の法改正は、単なる規制強化ではありません。日本の労働市場が多様性を真に受け入れ、その価値を最大化するための転換点なのです。
「義務だから仕方なく」ではなく、「この変化を成長機会として活かしたい」という意思を持つ企業こそが、これからの時代に持続的な競争優位を築いていけるでしょう。
障害者雇用は、もはや「特別な取り組み」ではありません。組織の多様性と包摂性を高め、イノベーションと成長を促進する、経営戦略の中核となる重要な要素なのです。
参考文献・データソース
- 厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査」(2023年)
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「障害者の就業状況等に関する調査研究」(2017年)
- 厚生労働省「雇用分野における障害者への差別禁止・合理的配慮」
注釈
¹ 企業の課題調査:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査」により、多くの企業が採用から定着まで一貫した支援体制の構築に課題を抱えていることが明らかになっている。特に法定雇用率達成を優先する企業ほど、継続的な価値創造に結びついていない傾向がある。
² 離職率データ:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の「障害者の就業状況等に関する調査研究」(2017年)によると、精神障害者の1年後職場定着率は49.3%となっており、約50%が1年以内に離職している。
³ 価値創造事例:厚生労働省の「雇用分野における障害者への差別禁止・合理的配慮」ガイドラインおよび各種調査研究により、戦略的に障害者雇用に取り組む企業では、組織全体のパフォーマンス向上、イノベーション促進、企業ブランド向上などの価値創造効果が確認されている。
ポシュロウラボでは、一人でも多くの「自分らしく働く」を実現するため、企業の皆様と一緒に歩んでいきます。ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお声がけください。